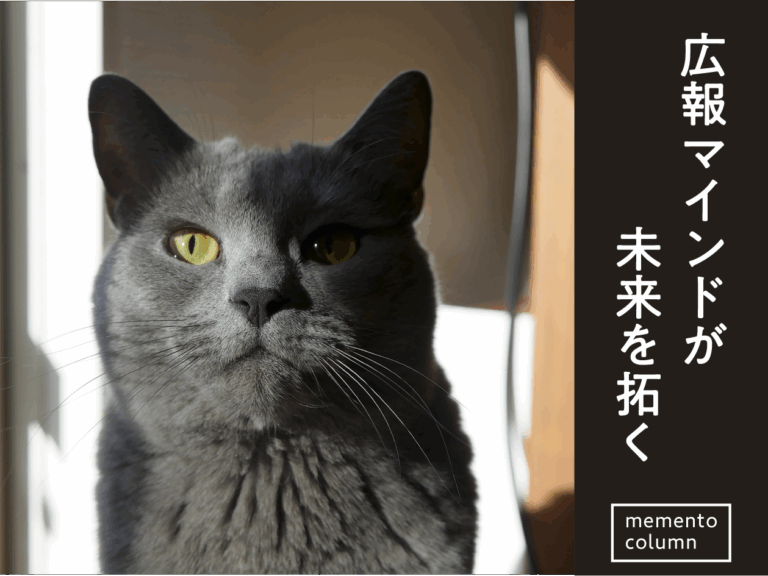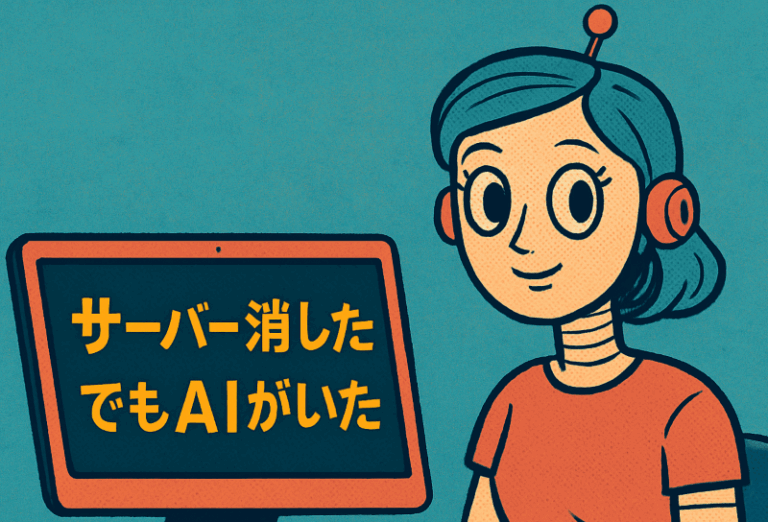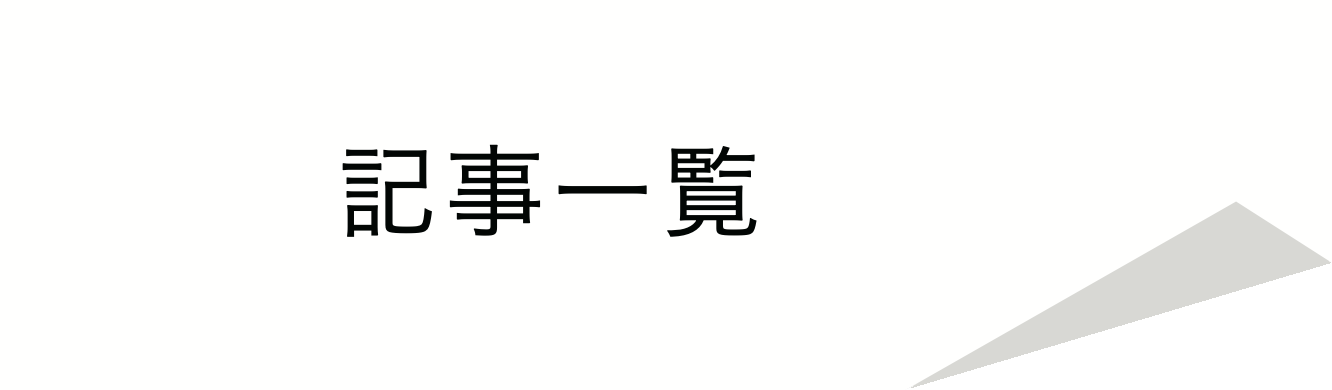今回は、広報は単なるマーケティング手段のひとつではなく、経営そのものである、というお話です。
「うちは広告もしていないし、マスコミに出る規模感じゃないから広報はいらない」
「広報って有名企業がやるものでしょ?」
「製品やサービスを作るのが先。広報は余裕ができたら」
こうした声を、これまで何度も耳にしてきました。
「広報はいらない」という考え方。実はこれこそが、中小企業成長の壁になってしまうのでは?もったいないなとそのたびに感じています。
広報を「マスコミにタダで紹介してもらってモノやサービスをヒットさせる手段」とか、広報担当者を「プレスリリースを出す係」「メディア対応係」=作業員のように考える経営者の方が多いかもしれません。しかし真の広報はもっと広義で、経営者の意思を社員、取引先、顧客そして社会に伝え、理解と共感につなげる「翻訳者」であり「補佐役」。つまり、広報とは経営の一部なのです。
ここで最も大切なことは、翻訳対象となる「原文」を持つのは経営者自身だということです。どれだけ優秀な広報担当者や外部支援者がいても、トップが伝えるべき自分の言葉を持っていなければ、翻訳は機能しません。採用で人が集まらない。営業内容がバラバラ。取引先や顧客に自社の価値観がイマイチ届いていない。こうした悩みの根っこには、経営者自身が表に立って語っていないパターンが多いのです。
例えば、支援している J-Workout という脊髄損傷者専門ジムでは去年から、9月5日の「国際脊髄損傷の日」に合わせて「知られざる脊髄損傷のリアル」を伝えるニュースレターを発行しよう、ということになりました。
今年はそこに「防災の日」(9月1日)を掛け合わせ、災害が相次ぐ国内情勢と、代表が日々募らせている脊髄損傷者の命に係わる避難対策への想いをつなげたいと考えました。
そこでまず、代表に“思いの丈”をコラムにしていただきました。次に、その要約を客観的温度のニュースレターにまとめ、熱いコラムはリライトした上で参考資料として添えました。さらに、関心・共感を抱いた記者さんに取材をしていただけるよう本年度の避難訓練実施を提案、ニュースレター内に様子を取材できる旨(取材案内)も入れ込みました。(取材の有無に関係なく、社内的意味&記録コンテンツとして広報資産になる点がポイント)。
結果、毎日新聞・東京新聞・神奈川新聞の3紙が取材に訪れ、社会性の高い記事を書いていただけました。
経営者が持っていた「語れること」を広報の視点で翻訳したことで、報道機関が「ニュースにする価値」を感じてくださった実例です。
だからぜひ、経営者の方には「広報マインド」を持っていただければと思います。
広報マインドとは前述の通り、広報業務を導入するかどうか、広報担当者を雇うかどうかではありません。自社を社会の一員として俯瞰し、何をもって社会に貢献したり喜んでもらったりするのか、どんな責任を果たすのかを血の通った言葉にすることです。
そしてそれを適切に伝え続けることで、社員、取引先、顧客、社会が同じ言葉で語ってくれるようになり、企業に対する誇りや応援したくなる気持ちが広がる未来が拓けていきます。
それなら、AIに投げて手っ取り早く言語化すればいい、と思うでしょうか?確かに、会社紹介文や求人広告、定型的な広報文であれば素早くそつなく仕上がるかもしれません。でもAIは、自動的に情熱やストーリーを宿すことはできません。いきいきとした、生命力ある「届く」言葉を生み出せるかどうかは、やはり経営者が何を語るかにかかっているのです。
同時に現代では、言葉の選び方やちょっとした誤解がSNSでの「炎上」につながってしまうことがあります。これはあらゆる会社に起こりうる表裏一体のリスクです。そのため、一方的に語るのではなく受け手に配慮しながら発信するという広報の基本マインドが、一層重要になっています。
ちなみに海外では、1990年代後半からCCO(最高コミュニケーション責任者)が経営幹部になるケースがあり、経営と広報は別物ではなく同じテーブルで意思決定されるものという認識が日本よりも広がっているようです。
とはいえもしも専任の広報担当を採用する余裕がない、あるいは採用しても活用しきれないと感じる場合は、外部に頼るという選択肢もあります。外注の方法はまるっと任せる形から、コンサルや社内スタッフの指導的な支援まで幅広く、会社の状況に合わせて柔軟に相談できるはずです。
広報を「経営の翻訳者」としてうまく活かすことができれば、企業は今より確実に前に進む力を持てるに違いありません。