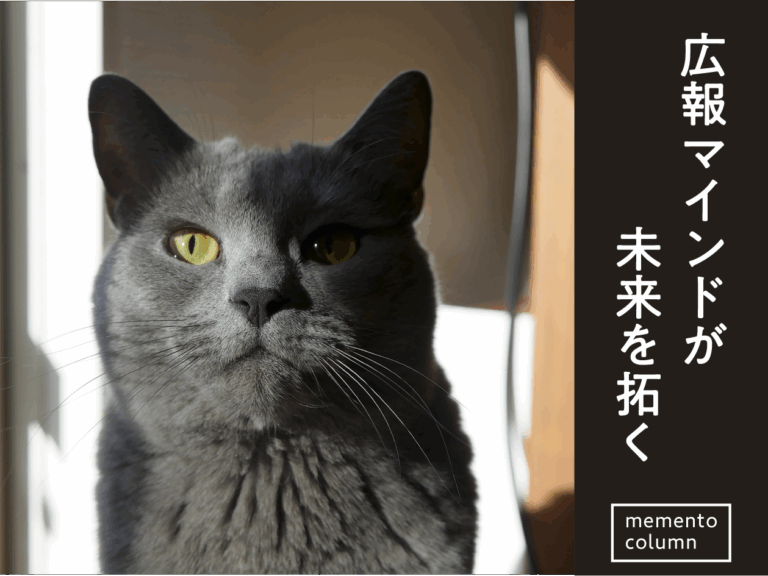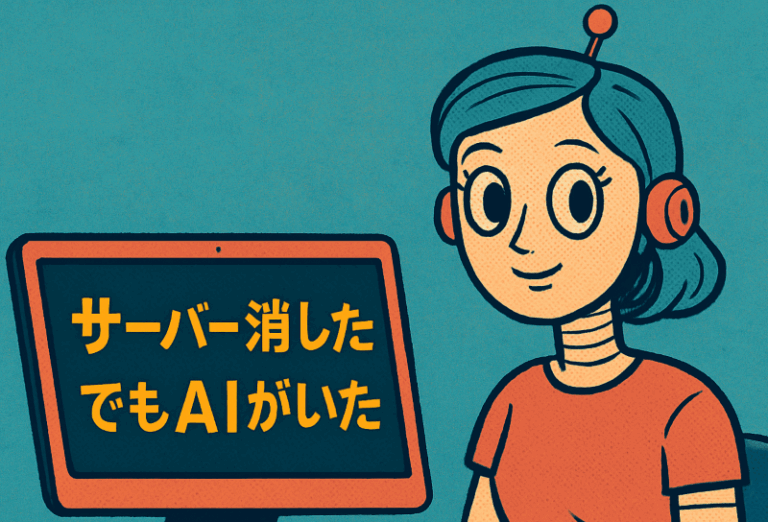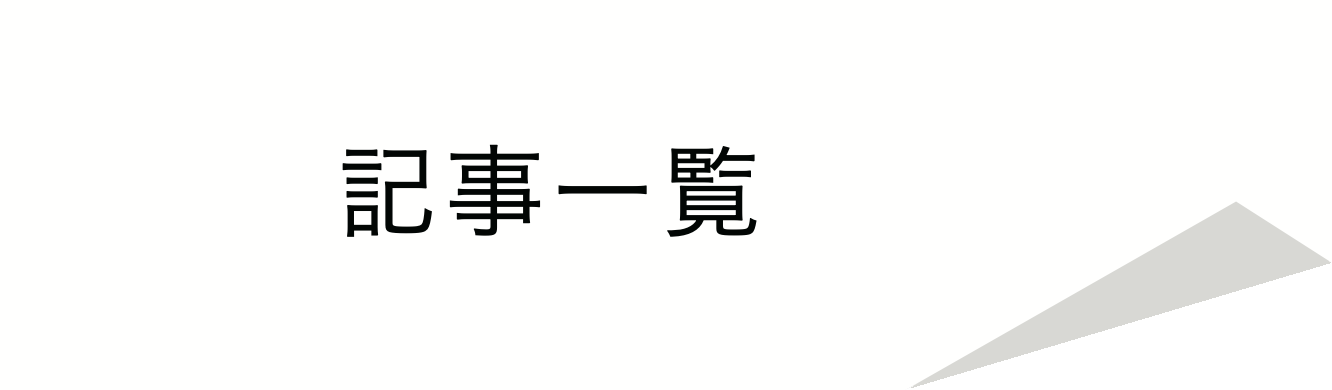インフルエンサーをはじめ影響力を持つ人たちによる美容・健康情報が問題視されるのをしばしば見かけますが、PRという仕事も、危ういネタ拡散の片棒を担いでしまうリスクと背中合わせです。
だから自分はそうなってはいけないし、クライアントさまが無防備に突っ込んでいきそうだったら全力で盾にならねばいけないと、まずは主に化粧品業界における薬機法規制を学ぶ「コスメ薬事法管理者」の資格を取得しました。
資格の勉強は「どういったことがどうNGなのか」という基本姿勢を学ぶイメージですが、知っているといないとでは大違い。生活者としても、巷にあふれる情報を読み解けるだけでなく、そこに「言ったもの勝ち」「売れさえすればOK」みたいなブランドの姿勢が透けて見えて「ああ、共感できないな」と取捨選択する判断材料にもなります。
プロとしてリリースやニュースレターなどのコンテンツを作成する際には、看板に偽りなしという緊張感と、いただいた情報を疑ったり検証したりする(失礼ながら!)しつこさ、そして表現や理論をチェックする手元資料で臨みます。
<活用している資料>
「健康食品・化粧品・雑品他健康美容 代替表現集」
「敏感肌の診療」
「皮膚は考える」
「日本化粧品検定テキスト」
個人的には、化粧品が肌に合わないケースが多いこともあり、科学的根拠ある製品や情報が好きではあります。が、一方で、「それ以外はダメ」となってしまうのも違うと思います。科学的にOKでも合わないものもあるし、何より化粧品を使う、スキンケアをする大切な要素に「楽しみ」があると思うからです。
あまたある情報を取捨選択するまでは理論(知識)を盾にして、その先は、自分にフィットする、心地いいものを選ぶ。そうやって自分の感覚に耳を澄ますことも、「正しく生きる」だけでなく「豊かに生きる」上で、同じくらい大切だと思います。
かつて本当に肌が弱くて、皮膚科で推奨されているドクターズコスメしか使えなかった(と思い込んでいた)とき、自分にとっては使い心地が悪いし見た目も好きではないもののコンディションキープはできるから…という気持ちで行うスキンケアは、まったく楽しくありませんでした。「何使っているの?」って聞かれたくない!なんて、劣等感みたいなものまでありました。
でも今は、敏感肌でも使えて見た目も使用感もいい商品がたくさんあって、自分が喜べる製品との出会いをあきらめなくていい時代になりました。それだけで毎日がちょっと潤うわけだから、化粧品の心への影響は、やっぱり置き去りにできませんよね。
PRに携わる者として、また、お肌よわよわ経験を持つ者として。
製品やブランドを選ぶための、適切なだけで終わらない豊かな情報発信を、引き続き肝に銘じていきます。