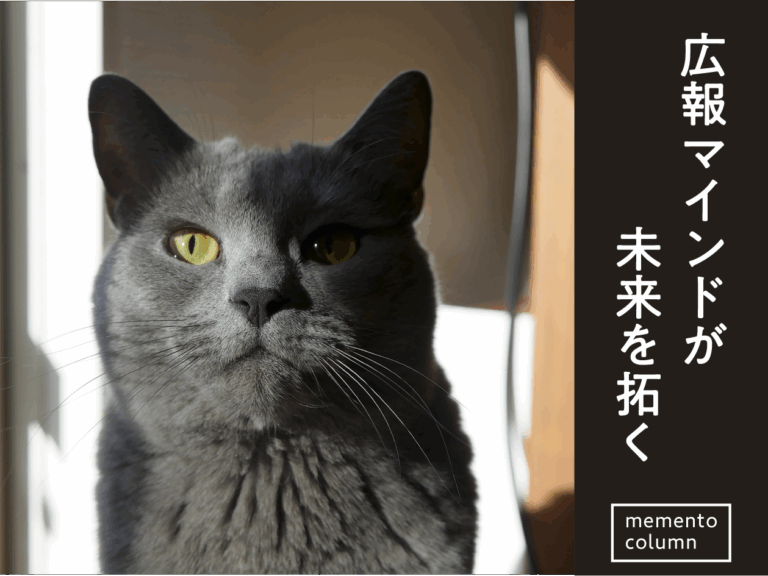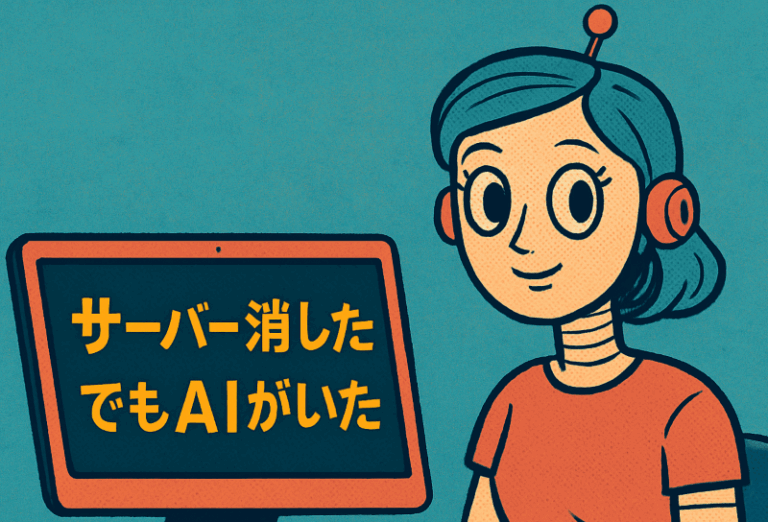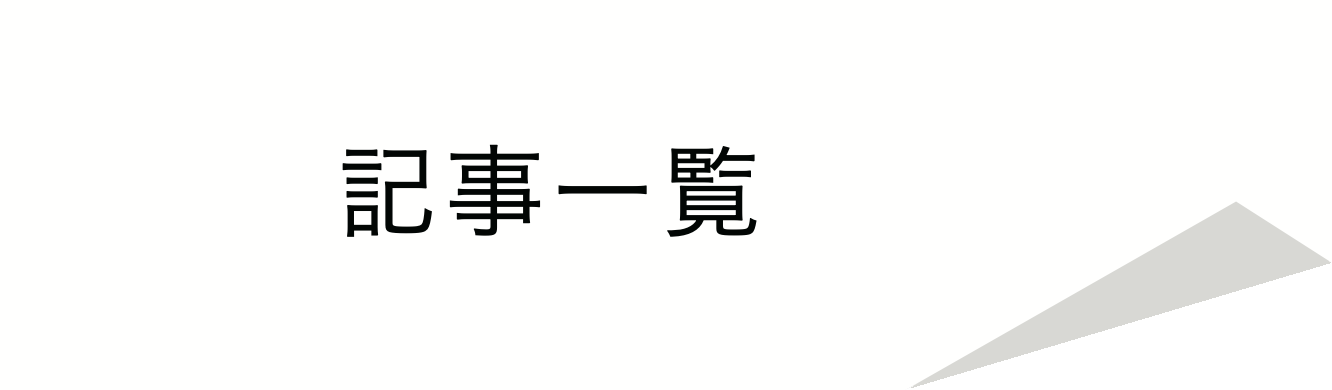美容系のSNSにおいては、製品に関する投稿で「#PR」をつけるのが“お作法”のようになっているように感じる今日この頃。 なんだか、タグが独り歩きしているような…
そこで今回は、PRの仕事に携わる立場から、「#PR」本来の役割について考えてみたいと思います。
“ステマ”で知られるステルスマーケティングという言葉があります。 広告であるにもかかわらずそれを隠すこと、いわゆるサクラやヤラセのことです。
さも「個人の感想」であるかのように発信することは違法であり、主導した企業やブランドの信頼は大きく損なわれます。そんな重大なリスクであるステマを恐れるがゆえに、「#PRをつけさえすればステマ認定されない」「とりあえず#PRを入れておけば安心」という対応が一般化しているように見えることが少なくありません。
本来、投稿が広告に該当するかどうかは、企業からの提供や報酬の有無、投稿内容への指示の有無といった“関与の程度”によって、法的に判断されます。そして、広告にあたると判断された投稿にのみ、「広告であることの明示」が必要になります。つまり、「#PRと書いたから広告として扱われる」のではなく、「広告だから表示義務がある」のです。ちなみに、商品を提供して「気に入ったら紹介してください」とだけ伝えて終わる場合は、内容の指定がないためステマにはあたりません。ただし、紹介によって将来的な報酬が示唆される場合には、ステマに該当する可能性があります*。
*元政府委員の弁護士が社主を務める薬事法ドットコムのガイドラインによる
インフルエンサーとそのフォロワーの関係においては、#PR表記が「企業との関係をきちんと明かしている誠実さ」=信頼の印や仕事の実績として受け取られる要素があるようです。その結果、「#PRでもこの人が紹介するなら」と読み進めてもらえ、内容次第でしっかり反響に繋がることもあるでしょう。
一方、情報を主体的に選ぶ読者やフォロワー外の人においては、#PRと書いてあるだけで「あ、広告か」と「スルーすべき投稿」になってしまうことが少なくないと思われます。
そもそもPR(パブリック・リレーションズ)とは、“相互に信頼で結ばれた関係”を意味する言葉です。それがいつの間にか「広告案件」の代名詞になり、「売りたい側」からのプッシュを表す言葉に見えてしまうのは、「本来のPR」に情熱を傾ける身としてなんとも切ない現状です。
そのような状況下でまず私にできることは、宣伝側のリテラシーを高めるサポートをすること。
#PRのルールへの理解を促し、乱発を防いでいくと同時に、#PRの投稿内容そのものが魅力的になる設計をバックアップし続けること。
なお、魅力的な投稿内容の実現には、完璧な「指示書」だけでは不十分です。
目に見えない・数値で表せない「語りたくなる想い」をかきたてる、企業やブランドならではの血の通ったコミュニケーションがやっぱり欠かせないと思います。
企業やブランドの想いの翻訳家として「手間暇」をいとわない本来のPRパーソンたちには、まだまだ役に立てることがたくさんあると信じています。